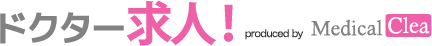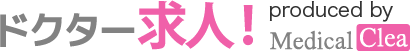4月からの法改正――かかりつけ医機能報告制度、育児・介護休業法改正、高年齢者雇用安定法改正
新年度を迎え、4月から新たな制度のスタートや改正法の施行があります。ここでは、クリニックの経営にもかかわりのある、主な新制度・法改正をご紹介します。
■「かかりつけ医機能報告制度」の創設
2023年に医療法が改正され、2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
かかりつけ医機能報告制度は、慢性疾患をもつ高齢者などを地域で支えるために必要な“かかりつけ医機能”について、各医療機関から都道府県に定期的に報告してもらい、その内容を一般に広く公表するとともに、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討する、というものです。
報告の対象となる医療機関は、特定機能病院と歯科を除く、全病院・診療所です。
報告内容は、「1号機能」と「2号機能」の2段階に分かれています。
医療機関からの報告は、毎年度行われ、初回の報告は2026年1月から3月の予定です。詳しくは、厚労省「かかりつけ医機能報告制度」のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
■育児・介護休業法の改正
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるよう、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職を防ぐための改正が行われます。
①子の看護休暇の見直し
対象となる子どもは、従来は小学校就学前に限定されていましたが、「小学校3年生修了まで」に拡大されました。また、改正前は労使協定を結ぶことで「継続雇用期間6か月未満」の人は対象から除外できましたが、この除外規定が撤廃されました。
②残業免除の対象拡大
これまで、3歳未満の子どもを養育する労働者から請求があった場合には、事業主は、所定外労働(残業)を命じることができませんでした。その対象が、「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されました。つまり、小学校就学前の子どもを育てているスタッフから請求があった場合には、残業はさせられないということです。
③介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
改正前は、労使協定を結ぶことで、「継続雇用期間6か月未満」の人を介護休暇の取得対象から除外できましたが、この除外規定が撤廃されました。
④介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるよう、事業主は、(1)研修の実施、(2)相談窓口の設置、(3)事例の収集・提供、(4)利用促進に関する方針の周知――のいずれかの措置を講じることが義務化されました。
⑤介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護に直面したことを労働者から伝えられたら、事業主は、介護休業制度について周知し、介護休業の取得や介護両立支援制度の利用の意向を個別に確認しなければなりません。また、介護に直接する前(40歳等)のタイミングで情報提供をすることも、新たに義務づけられました。
これらはすべて2025年4月1日から施行されます。詳細は、厚労省「育児・介護休業法について」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
■高年齢者雇用安定法の経過措置終了
2025年3月31日までは、「継続雇用制度」における経過措置が認められ、労使協定を締結することで、定年後に雇用を継続する労働者を限定する基準を設けることができました。この経過措置が終了し、2025年4月1日以降は、希望するすべての労働者に対し、事業主は65歳までの雇用の機会を確保しなければいけません。
なお、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではなく、次のいずれかの措置を講じる必要があります。
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
詳しくは、厚労省のホームページ「高年齢者雇用安定法の改正~『継続雇用制度』の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
- 会員登録のメリット
- 必要事項が登録されているので求人応募が簡単。
- 優先的に非公開求人や厳選求人をご紹介します。
- 会員のみに開示している情報もweb上で閲覧可能です。